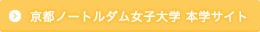

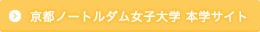

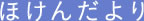
2014年12月22日
ノロウイルスについて
ノロウィルス
毎年冬に流行する感染性胃腸炎です。毎年12月から3月をピークにして全国的に流行します。
●ノロウィルスとは?どうやって感染するの?
非常に感染力が強く、少ないウィルスで多くの人に感染します。便や嘔吐物として体の外に出た後も感染力が衰えません。汚染された食品(貝類など)からの「経口感染」と、ヒトからヒトへの「糞口感染」(感染した人の便や嘔吐物、またはそれによって汚染されたものを介して経口的に感染する)があります。
●症状は?
ウィルスが体に入って1~2日後に、激しい吐き気・嘔吐・下痢・腹痛・発熱などの症状が出ます。特に嘔吐が強い傾向にあり、「冬季嘔吐症」と呼ばれていたこともあります。通常1~2日で治まり、人によっては発症しなかったり、軽い風邪のような症状ですむ場合もあります。
●治療法は?
今のところノロウィルスに有効なワクチンや抗ウィルス剤はありません。下痢や嘔吐により脱水状態となるので、脱水を防ぐため水分をしっかりとり、脱水症状がひどい場合は病院で輸液などの治療も行われます。一般に対症療法のみで1~2日で回復します。ただし、抵抗力の弱い高齢者や乳幼児などでは重症化することがあり、入院が必要となる場合があります。
●予防法は?
食中毒の予防
(1)食品は85度以上で1分以上加熱する。
(2)調理器具などは殺菌して、二次感染を防ぐ。
*二枚貝に注意!!・・・カキやハマグリなどの二枚貝は、海水を取り込んでその中のえさを食べていますが、その際ノロウィルスも一緒に取り込まれて体内で濃縮されるため、食中毒の原因になりやすいと考えられています。ウィルスがたまる心臓部(黒い部分)を中心にしっかりと火を通せば、食べても大丈夫です。
感染拡大を防ぐ
(3)便や嘔吐物は乾燥しないうちに処理する。
→ノロウィルスは乾燥すると空中に漂い、これが口に入って感染することがあるので、汚物は速やかに処理 し、乾燥させないようにしましょう。
(4)感染源となりうるものは、残らず確実に処理する。
【嘔吐物や便の処理方法】
① 嘔吐物や便などの後始末をするときは、使い捨ての手袋やマスクを着用する。
② 汚物はペーパータオルなどで静かにふき取る。
③ 汚物をふき取った後の床などは、次亜塩素酸ナトリウム(0.02%)で浸すように再度ふき取る。
④ おむつやふき取りに使用したペーパータオルなどは、ビニール袋などに密閉して廃棄する。
→廃棄物が十分浸る程度の次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)を入れることが望ましい。
⑤ 処理の後の室内は、十分に換気する。
※ 次亜塩素酸ナトリウム・・・ノロウィルスに対しては、消毒用アルコールは効果が薄いため、塩素系の漂白剤(市販名:キッチンハイターなど)を使用します。例として、キッチンハイターを使用した場合の濃度の調整方法を示します。(販売元に確認すると、出荷時は塩素濃度5%程度だが徐々に薄くなってくるとのこと。今回は5%として計算します。)
水500mlに対し、次の量のハイター液を加えます。
【次亜塩素酸ナトリウムの稀釈方法】
濃度 水の量 ハイターの量 ペットボトルのキャップ
0.02% 500ml 2.5ml 1/2(半)杯程度
0.1% 500ml 10ml 2杯程度